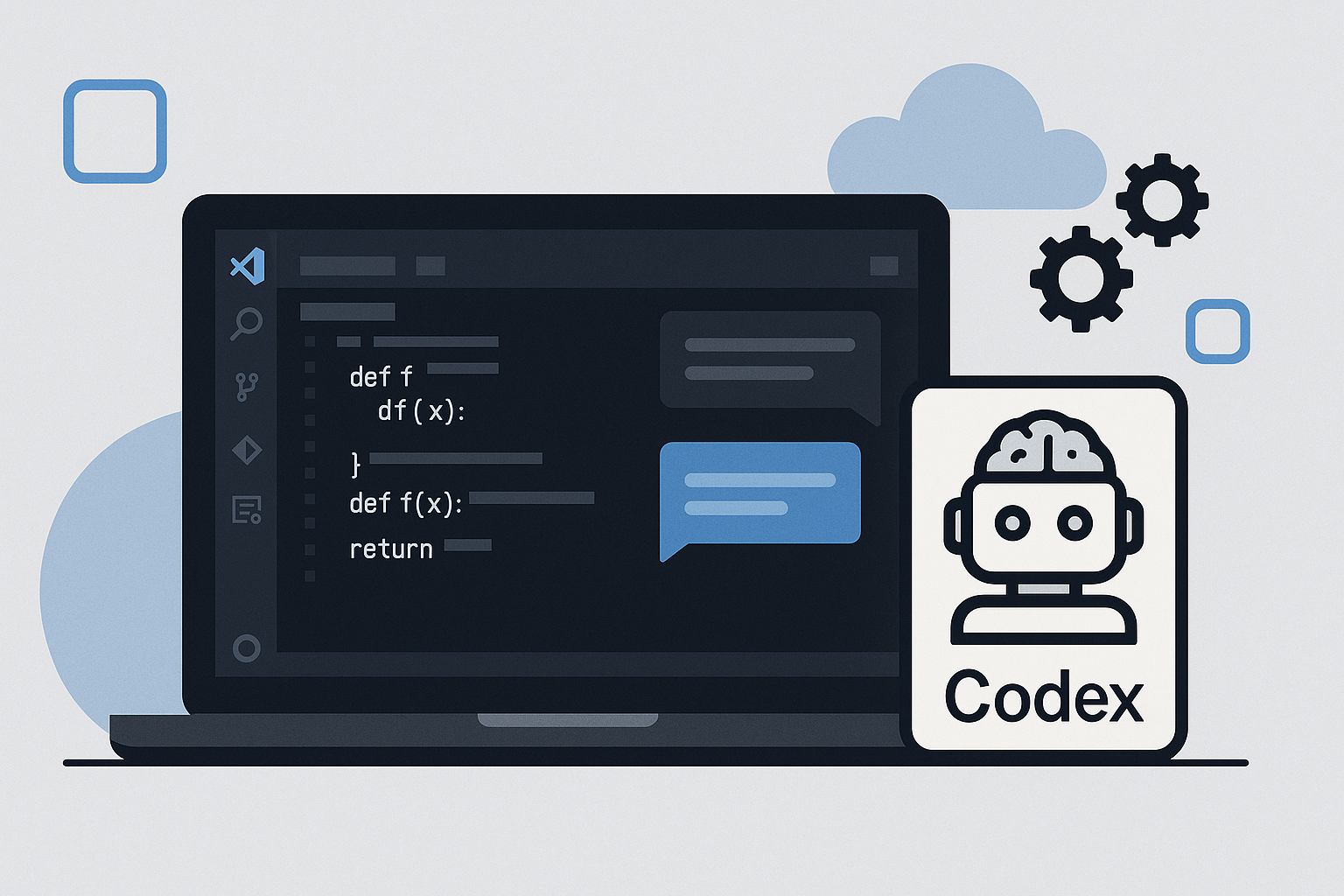
前回の記事では、VSCodeに「Codex – OpenAI’s coding agent」を入れてGPT-5を利用できること、そして“思考モード”を切り替えられる体験について紹介しました。
今回はその続編として、思考モードの実像や承認モードの仕組み、クラウド連携による活用術をより深く掘り下げてみます。
Codex拡張の基本設計
- 導入はVSCodeマーケットプレイスからインストール。
- OpenAIアカウントでサインインするだけで利用可能(APIキーの手入力は不要)。
- エディタ内でのペア作業に加え、クラウド環境へタスクを委譲する仕組みを持つ。
この二層構造により、軽快な補完から大規模リファクタまでをシームレスに行える。
GPT-5の思考モードを改めて整理
Codexで体感できる「Instant / Balanced / Thinking」の違いを、実務視点で掘り下げると次のようになる。
-
Instant(即応型)
- 最小限の探索で素早く返答
- コード補完や短い説明に最適
- “同僚に一言聞く”感覚で使える
-
Balanced(主力型)
- 速度と精度の中間
- レビューや記事草案にバランス良く対応
- “頼れるペアプログラマー”の感覚
-
Thinking(深掘り型)
- 応答まで数秒かかるが、論理展開が豊富
- 設計検討やバグ調査に強い
- “先輩エンジニアにじっくり相談”する感覚
ここで大事なのは、「速さ」と「深さ」のトレードオフを自分で選べること。
タスクの性質に応じて切り替えるのが生産性を左右する。
安全性を守る承認モード
Codexは権限の段階設定も特徴的だ。
- Chat:会話のみ。コードや環境を勝手に変えない。
- Agent:作業ディレクトリ内の変更は自動で行うが、外部アクセスは要承認。
- Agent (Full Access):ネットワークや広い範囲を操作可能。実験環境での利用推奨。
これにより、「誤操作が怖いからAIを信用できない」という不安を軽減できる。
クラウド連携でできること
Codexは、ローカルだけでなくクラウド実行環境とも連動する。
- 大規模テスト生成やリファクタを外部で実行
- 結果をレビューしてからローカルに適用
- 手元の思考を止めずに、バックグラウンドで作業を並行化
この仕組みは、**「人は方向を示す、AIは作業を回す」**という役割分担を強化してくれる。
実務での使い分けパターン
- 仕様整理 → Thinking
前提や制約を明示して漏れを減らす。 - 初版実装 → Balanced
動く最短コードと最低限のテストを確保。 - 微修正ラッシュ → Instant
名前付けやコメント修正を秒で回す。 - バグ追跡 → Thinking
差分の副作用やテスト観点を抽出。 - クラウド委譲 → Balanced/Thinking
重いタスクは外に投げ、結果だけ吸収。
まとめ:AIの“ギアチェンジ”を手元で
Codex拡張を通じて感じたのは、GPT-5を「速さ優先/深さ優先」で切り替えられる」新しい作業体験だ。
- 軽作業はInstant
- 本流はBalanced
- 設計や調査はThinking
さらに承認モードやクラウド連携を組み合わせれば、安全かつ効率的にAIを“相棒”として活かすことができる。
👉 関連記事: